(1) (2) (3)
80年代後半から志願院のプログラムはより社会的な関わりを中心にしたものへと変化して行きますが、それは知的なものに価値を置くギリシャ的な人間理解からの大きな転換だったと思います。すこし難しいですが、受肉の神学に基づいた人間理解と私の読んだ養成に関する文書には書いてありました。キリストが神でありながら自分を無なしくして人間となったということです。キリストは肉を受けたのです。そこには、肉体に代表される物質的なものや感情、世俗的なものを否定せずに霊的なものに統合していく人間理解があると思います。つまり人間の成長とは単に知識を増すことではなく、自分自身の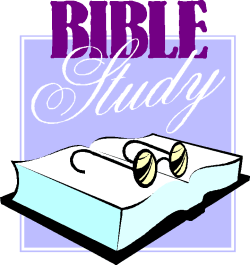 様々な面を霊的なものへと統合してゆく歩みだと言うことです。そこには社会や世間を俗な世界として否定するのではなく、その社会や世間と関わりつつ霊的な高みへと自分を変えて行く回心の道こそ人間の成熟の道であり、養成が目指すものだという考えが見えて来ます。その意味で志願院では社会的な関わりを否定しません。しかし、その関わりを霊的な関わりの中でどのように位置付け、志願者の中で統合してゆくのか?そのプロセスなり方法論が今の志願院に問われていることだと思います。 様々な面を霊的なものへと統合してゆく歩みだと言うことです。そこには社会や世間を俗な世界として否定するのではなく、その社会や世間と関わりつつ霊的な高みへと自分を変えて行く回心の道こそ人間の成熟の道であり、養成が目指すものだという考えが見えて来ます。その意味で志願院では社会的な関わりを否定しません。しかし、その関わりを霊的な関わりの中でどのように位置付け、志願者の中で統合してゆくのか?そのプロセスなり方法論が今の志願院に問われていることだと思います。
例えば社会的な関わりとして、ボランティア活動に参加するなど様々な関わりを志願院ではします。その関わりが単に良いことをしたという自己満足や、苦しい修行の一つとして自分を磨く道具だけで終わらない何かが求められているのではないでしょうか。自己満足で終わらないためには、自分を明け渡す他者への開きがなければできないことです。その他者への開きは、単に人付き合いが良いとか、明るい性格とかいうものではなく、自分を無にするというキリストの生きた生き方です。私達にとって養成のモデルはキリストなのです。それゆえより一層の御言葉を中心とした養成が求められていると言えるでしょう。
知識中心から社会活動へと志願院のアクセントは80年代後半を軸に移行して行きましたが、ここ数年、私の個人的な印象ではそのような養成に行き詰まりを感じています。それは、10年前と状況が大きく変化し、社会や人々の意識も変化して来た結果だと思います。 10年前、第二共同体という神学生共同体の社会意識の盛り上がりがあった時期における志願者や神学生の意識と現在の志願者や神学生の意識は大きく違っていると思います。その当時あまり問題にならなかった霊性と活動の分離は、現在もっとも深刻であると個人的には感じています。そのような分離が深刻化しているメカニズムを考えると、養成はもっと社会的な関わりや小さくされた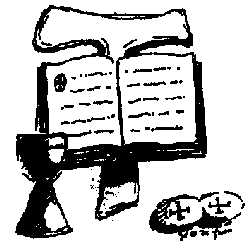 者たちの中で行わなければいけないというプレッシャーがどこかにあり、養成者はそれに答えるべく様々な社会的なプログラムを準備し、志願者はそのプログラムに応えなければならないという意識から頑張るという構図のせいだと思います。そこには良き養成者、良き志願者という良い子を演じるロールプレイ(役割演技)が生じ、そのため志願院で社会的な活動をしてもそれが単に自己鍛練などにすり代わってしまい、外面的にただプログラムをこなすだけのものになってしまったように感じるのです。 者たちの中で行わなければいけないというプレッシャーがどこかにあり、養成者はそれに答えるべく様々な社会的なプログラムを準備し、志願者はそのプログラムに応えなければならないという意識から頑張るという構図のせいだと思います。そこには良き養成者、良き志願者という良い子を演じるロールプレイ(役割演技)が生じ、そのため志願院で社会的な活動をしてもそれが単に自己鍛練などにすり代わってしまい、外面的にただプログラムをこなすだけのものになってしまったように感じるのです。
そのような問題意識を私は持っているのですが、その観点から今後養成は御言葉中心へと向かうべきだと感じているのです。御言葉とはキリストが生きた生き方です。今以上に御言葉に向き合い、キリストの生き方に真剣に向き合って行くことなしにこれからの養成は語れないでしょう。勉強や社会活動、ボランティアはともすると逃げ場所になります。つまりそれらが自己満足や自己実現、良い子を演じる場に終わってしまう場合があるし、現在では10年前にくらべその点が特に深刻です。それは中身のない外面的な良さです。イエスがマルタに言われたように、私達は大切なことを見失っているのではないでしょうか。でも、どうやって御言葉と向き合いながら養成を進めていったら良いのかと言う具体的な方法論になると、とんとアイデアが浮かびません。そんなことを考えながら日々悩んでいます。
|