(1) (2) (3)
規則や知識中心の養成から御言葉中心の養成へ
フランシスコ会の養成に関する文書を読んでいてこんなことが書かれていました。ヴァチカン公会議前の養成は非人格的・非歴史的だったと言うのです。つまり養成の中心は世間から隔離し規範を教えることであり、それに従っているかどうかでした。そこでは外面的な良さだけが強調され、その人物の人格的な成長や成熟という内面的なものはあまり考慮されなかったということです。また、非歴史的とはたぶん、養成から時代を切り捨ててしまったということでしょう。つまり時代の動きや社会の動きなどは養成 の中で考慮されることなく世間や社会、時代から断絶した養成の事をいうのだと思います。そのような前時代の養成の反省から現代の養成では人格的な面、すなわちその人の内面的な成熟や、時代や社会との関わりを重視したものとなってきたのです。 の中で考慮されることなく世間や社会、時代から断絶した養成の事をいうのだと思います。そのような前時代の養成の反省から現代の養成では人格的な面、すなわちその人の内面的な成熟や、時代や社会との関わりを重視したものとなってきたのです。
もう一つ、そのフランシスコ会の養成に関する文書の中で興味深かったのは、人間理解の違いについてです。公会議前はどちらかというとギリシャ的な人間理解が強かったというのです。ギリシャ人は人間を霊と肉に分けて考えました。そして、より価値のあるものは霊の方で肉は劣るものという考えです。この考えはより知的なもの、理性や精神という世界を最高の世界と考え、感情や肉体的なもの、物質的なものはより価値の低いものという考えが背景にあります。この考えに基づいて人間を養成した場合、知的なものを最優先とし、感情や肉体的、物質的なものは否定されて行きます。
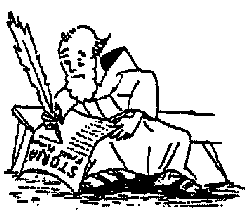 このことは日本のフランシスコ会の志願院の変遷によく現われているように思います。公会議前の志願院は当初ラテン課と言ってラテン語を勉強するのが志願院の主なプログラムでした。その頃を志願院で過ごした先輩方から聞くのは、その当時、ラテン語ができる人が次の修練に進み、ラテン語のできない人は帰されたということです。つまりラテン語の能力で召命を判断していたということです。その後、志願院が六本木修道院や名古屋修道院などに移っても志願院のプログラムは大学で勉強することが中心であったと聞きました。つまり知的な能力というのが養成の大きな目標になっていたと言えるのではないでしょうか。 このことは日本のフランシスコ会の志願院の変遷によく現われているように思います。公会議前の志願院は当初ラテン課と言ってラテン語を勉強するのが志願院の主なプログラムでした。その頃を志願院で過ごした先輩方から聞くのは、その当時、ラテン語ができる人が次の修練に進み、ラテン語のできない人は帰されたということです。つまりラテン語の能力で召命を判断していたということです。その後、志願院が六本木修道院や名古屋修道院などに移っても志願院のプログラムは大学で勉強することが中心であったと聞きました。つまり知的な能力というのが養成の大きな目標になっていたと言えるのではないでしょうか。
次ページ
|