私の中に「ファリサイ人」が隠れています。
誰にとっても時々このような思いがあると思います。でも、私が志願者の責任者になってからは、ファリサイ人に対するイエスの言葉に特に心が痛みます。
そのとき、イエスは群衆と弟子たちに、次のように仰せになった。「律法学者やファリサイ派の人々は、モーセの座についている。だから、彼らの言うことはすべて実行し、また守りなさい。しかし、彼らの行ないを見ならってはならない。彼らは言うだけで、実行しないからである。彼らは重い荷をたばねて人の肩に負わせるが、自分たちはそれを動かすために指一本触れようとはしない。その行ないはすべて、人に見せるためのものである。たとえば、経札の幅を広くしたり、マントのふさを大きくしたりする。また、宴会の上座や会堂の上席を好み、広場であいさつされることや、人々から『先生』と呼ばれることを喜ぶ。しかし、あなたがたは『先生』と呼ばれてはならない。あなたがたの先生はただ一人であり、あなたがたは皆兄弟だからである。地上の者を『父』と呼んではならない。あなたがたの父はただひとり、天におられる父だけである。また、あなたがたは『教師』と呼ばれてはならない。あなたがたの教師はただ一人、メシアだけである。あなたがたのうちでいちばん偉い人は、かえってみんなに仕えることになるであろう。自ら高ぶる者は下げられ、自らへりくだる者は上げられる。(マタイ23:1−12)
小教区で働いていた時にも司祭として、信者の指導者としての自分が真っ先にこの言葉に問われていたように感じていました。
信徒や幼稚園の世話をし、何時も「神父様」とか「先生」と呼ばれたりして、自分は名前が付いているのに…自分の名前が懐かしく思う程でした。
小教区にいる間どの程度自己回心の道に進んで行ったか、また、どのぐらい人々の前でキリストの証しが出来たかは分かりません。覚えていることは、日本語で説教や他の話の準備をする時の辛さです。でも、日本語の難しさよりも辛かったのは、イエスの言葉を信者に繰り返して説明しながらも、教えていることを心から実行していない自分を見つめることでした。偽善者は惨めな存在です。心が満たされない淋しいものです。
「もっと祈らなければならない」と、朗読台から聞かせますが、個人では落ち着いた祈りの時間をなかなか作ろうとはしません。「互いに愛し合いましょう」とか「赦し合いましょう」とか「貧しい人々と連帯しましょう」と、神の言葉を利用して説得を尽くします。自分の心には神の愛はまだ留まっていないことに気がつきますが、それこそ宣教師の普通の苦しみで、当たり前の孤独だと思いました。淋しかったけど、苦しみを神に捧げるつもりで頑張っていきました。神父が疲れるものだというのは、当然ですね。偽善者にも安らぎがなく、本当の友達が少ないことも当たり前ではないでしょうか。
それにしても、教会では信者はミサに与ってからそれぞれの家に帰ります。神父の「ご苦労」が終わりゆっくりとテレビを見ながら食事が出来ます。
志願者の同伴者として桐生修道院に来てからは、そのような心の問題をもっと深く感じるようになりましたが、同時に安心感や仕事のやり易さにも恵まれたと思います。桐生では兄弟と共に生活するようになったからです。それで志願者を指導するのは私一人ではなく、共同体全体が協力しているのです。更に各々の特徴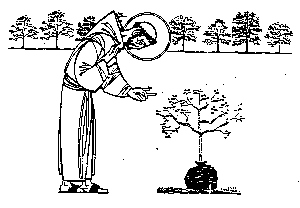 があって、助け合っている訳です。私は志願者と一緒にフランシスコの心を理解しようと勉強や分かち合いをしていますが、あの兄弟は既にそれを見せて下さっているのです。私が志願者の態度を直そうと怒鳴っても、この兄弟は無言で、既に自分の生き方だけで模範を見せて下さっているのです。祈りや兄弟に仕えることについてしつこく言っても、兄弟たちの方が毎日聖櫃の前で長い時間を過ごしたり、他人に喜んでもらえることを常に沢山なさっています。And so on… があって、助け合っている訳です。私は志願者と一緒にフランシスコの心を理解しようと勉強や分かち合いをしていますが、あの兄弟は既にそれを見せて下さっているのです。私が志願者の態度を直そうと怒鳴っても、この兄弟は無言で、既に自分の生き方だけで模範を見せて下さっているのです。祈りや兄弟に仕えることについてしつこく言っても、兄弟たちの方が毎日聖櫃の前で長い時間を過ごしたり、他人に喜んでもらえることを常に沢山なさっています。And so on…
勿論、個人として辛いときもあります。私の中のファリサイ人は休む時間がなかなか見つかりません。教会の信者はミサや聖書の勉強が終わって家に帰りますが、志願者や他の兄弟はいつも一緒にいるからです。辛いと言いますが、それは有り難いことでもあると認めなければなりません。言うだけで実行しないと、心に平和を得ることがなかなかないからです。志願者のお陰で常に自分にもまず誠実があるかどうかと問われて、絶え間なく自己回心へと招かれています。
しかしながら、大きな悩みが残っています。説明しにくいと思いますので簡単な例をもってやってみましょう。私はある兄弟に「自分を改めよ」と言えないし、他人の回心を求めることも出来ないでしょう。出来ることはその兄弟ではなくて、自分を改め、兄弟に対する態度を変え、聖霊の助けで自分が回心することだけです。兄弟がその後で変わるか、変わらないか、問題にならないはずです。
兄弟である志願者のそばでも同じなのでしょうか。志願者とは、修道生活への召命を確めるために、ある共同体に入り兄弟一緒に一年間を過ごすものです。志願者は求めるものです。「召命の識別のために助けをください。分からないことが沢山あります。一緒になって僕の生き方を見て僕がフランシスカンの生活に適切かを評価して判断を下さい」と。それなら、私が自分の召命に対して忠実に生きていないことを認めながらも、志願者の無言の願いに応えなければならないのではないでしょうか。言いかえれば、心から喜んで実行に移していないが、正しいと信じていることなら口先だけでも言うべきではないでしょうか。「心ははやっていても、肉体は弱いものだ」(マタイ二十六・四十一)。というような悩みです。
しかし心の中では兄弟と共に回心の歩みに一歩でも進めるチャンスが与えられていることに感謝しています。これこそ養成の真髄ではないでしょうか。
「兄弟にキリストについて話をするよりは兄弟のことをキリストに話す方がましです。」 というボンフェッファーの言葉が度々思い浮かびます。落ち着いて祈るときに神の計らいを感謝し、志願者が私の望み通りではなく、主のみ旨の通りに成長すればと願っています。たとえ私が指している道でなくても私たちが想像さえ出来ない新しい道でも良いと思います。私たちが夢に見ている明日のフランシスコ会を彼らに負わせる必要はありません。しかしフランシスコ会の刷新を丸ごと今の若い兄弟たちに任せる考え方は正しくないと思います。刷新なら全員が問われているのです。なぜなら、たとえ多様の道であろうとも同じ回心の歩みだからです。同じ福音からの呼びかけであり、唯一の主からの招きだからです。疲れや無関心などは福音からのものではありません。自分に捕われている私たち一人一人の心にその原因があるのではないでしょうか。
結局は、説教のようなものを書いてしまいました。赦してください。私の中に眠っているファリサイ人がちょっとの間、目を覚ましただけです。
後書き
この記事を書いている時に教会の祈りの中のある聖書の言葉に目が留まりました。
「あなた方が召されたのは、自由のためである。その自由を、肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えよ。律法全体は『あなたの隣人を自分のように愛せ』という一言に尽きる。」 (ガラテヤ5:13−14)
志願院養成担当者 アルフォンソ・プポ神父
|