丂丂恑楬巜摫偵寽柦側愭惗偨偪偲偁傑傝婥偑忔傜側偄惗搆偨偪丅偁傞崅峑偺俁擭惗偺偆偪懖嬈偡傞傑偱偵恑楬偺寛傑傜側偄惗搆偑俀侽亾嬤偔傕偄傞偙偲傪偁傞僥儗價斣慻偑庢傝忋偘偰偄偨丅俁擭惗偵側偭偰偐傜偱偼抶偡偓傞偺偱丄侾擭惗偺帪偐傜彨棃偺偙偲傪峫偊傞婡夛傪採嫙偟傛偆偲條乆側婇夋偑棫偰傜傟偰偄偨丅偦傟偵偟偰傕丄娭怱偺敄偄惗搆偨偪偑懡偄偺偵偼嬃偄偨丅恖惗偺堄枴傪峫偊偝偣傛偆偲寽柦偵側偭偰摥偒偐偗傞愭惗偨偪偺巔偑側偤偐妸宮偵尒偊偰偟傑偆丅
丂壗傪傗傝偨偄偺偐傢偐傜側偄偐傜丄乽偲傝偁偊偢丄僼儕乕僞乕傪傗傝側偑傜峫偊傞乿丄乽愱栧妛峑傕峫偊偨偑乧丅曌嫮偟偨偔側偄偟乧丅乿偲偄偆惗搆傕偄偨丅乽偁偊偰朻尟偡傞庒幰偑彮側偔側偭偰偒偨丅乿乽幐攕傗徴撍傪旔偗傞偨傔偵嵟弶偐傜娭學傪帩偨側偄丄昞柺揑側偮偒偁偄偟偐偟側偄丄偲偄偆孹岦偑嫮偄丅乿偲尵偆夝愢幰丅偄偭偨偄偙傟偐傜偺幮夛偼偳偆側偭偰偄偔偺偩傠偆偐丄偲怱攝偵側偭偰偒偨丅惗搆偨偪偲愭惗偨偪偑偳偙偐偱偡傟堘偭偰偄偰岎傢傞応偳偙傠偐揰傕尒偊側偐偭偨丅偙偺斣慻傪嵟屻傑偱尒側偐偭偨偺偱丄偳偺傛偆偵傑偲傔傜傟偨偺偐暘偐傜側偄偺偑巆擮偩偭偨丅
丂侾俋俋俋擭廐丄擔杮娗嬫偼僼儔儞僔僗僐夛搶傾僕傾娗嬫嫤媍夛偺擇偮偺崙嵺夛媍傪庡嵜偟偨丅偦偺偆偪偺堦偮偼梴惉扴摉幰偺夛媍丅僥乕儅偼丄乽僌儘乕僶儖壔偟偨悽奅偵偍偗傞彚柦懀恑偺偨傔偺摥偒乿丅奺娗嬫偐傜梴惉帠柋嬊挿偲彚柦扴摉幰偑棃擔偟偨丅嬨寧偵戝抧恔偑偁偭偨戜榩偐傜偺戙昞偑嶲壛偱偒側偐偭偨偑丄偓傝偓傝偵價僓傪庢摼偟偨儀僩僫儉偺孼掜偨偪偑嶲壛偱偒偨丅
丂偙偺夛媍偺拞偱丄尰戙偺庒幰偨偪偺摿挜丄壙抣娤側偳傪妛傃丄廋摴彚柦偵墳偊傞彽偒偺摥偒偑帩偮壽戣側偳傪尋廋偟暘偐偪偁偭偨丅搶傾僕傾偺屲偮偺崙偐傜側傞偙偺娗嬫嫤媍夛偺梴惉扴摉幰偼枅擭岎棳偲尋廋偺偨傔偵廤傑傝傪帩偭偰偄傞丅崱擭偺夛媍偼俀侽侽侽擭廐偵傾僔僕偱俁廡娫偵傢偨偭偰奐嵜偝傟傞乽彚柦扴摉幰偺崙嵺夛媍乿偺弨旛夛偺惈奿傕帩偭偰偄偨丅
丂僌儘乕僶儖壔偟偨悽奅乮幮夛乯偺摿挜偲偟偰丄嘆揱摑揑壙抣娤偑曵傟丄懡條側壙抣娤偲壜擻惈偑採帵偝傟偰偄傞丅嘇宱嵪偺暘栰偽偐傝偱側偔條乆側暘栰偱崙嫬偲偄偭偨傛偆側儃乕僟乕偑堄枴傪側偝側偔側傝偮偮偁傞偙偲丅嘊屄恖偺桪愭丄帺桼丄嘋僀儞僗僞儞僩丒僐儈儏僯僥傿壔丄僐儞價僯僄儞僗丒僗僩傾揑儊儞僞儕僥傿丄嘍悽懎壔丄側偳偑嫇偘傜傟傞丅偦傟偧傟僱僈僥傿僽側懁柺偲峬掕揑懁柺偑偁傝丄嶲壛幰偨偪偼崙傗暥壔丄惂搙偺堘偄傪挻偊偰偦傟偧傟偺懱尡傪暘偐偪崌偄堄尒傪岎姺偟偁偭偨丅
奺娗嬫偐傜偺曬崘偲島巘偵傛傞尋廋偲暘偐偪崌偄偱柧傜偐偵側偭偰偒偨偺偼丄彚柦懀恑偺摥偒偺壽戣偼丄庴偗擖傟傞懁偺巹偨偪偺傎偆偑戝偒偄偲偄偆偙偲丅彚柦偺懡偄娗嬫傕丄彮側偄丄偁傞偄偼杦偳乽側偄乿娗嬫偵傕嫟捠偺壽戣偑晜偐傃忋偑偭偰偒偨丅嘆僼儔儞僔僗僇儞揑惗偒曽傪偳偺傛偆偵採帵偡傞偺偐丅嘇巙婅偟偰偒偨庒幰偨偪偺楈揑丒恖娫揑惉挿傪偳偺傛偆偵巟偊傞偐丅嘊梴惉偵娭傢傞孼掜偨偪帺恎偺梴惉偺昁梫惈偲恖嵽晄懌乮愱擟幰偑彮側偄乯丅嘋偁偐偟偵側傞孼掜揑嫟摨懱偺惗妶偲岎傢傝偺廳梫惈丅
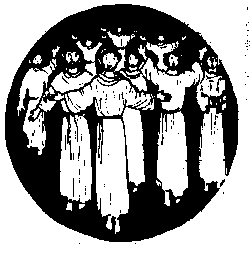
丂庤傪峀偘偰乽偙偙偑巹偨偪偺廋摴堾偱偡乿偲悽奅傪巜偟帵偟偨偲尵傢傟傞僼儔儞僔僗僐丅儃乕僟乕儗僗偺幮夛丄帺慠偺拞偱偺嫟惗丄孼掜揑娭傢傝偲惗偒曽偑傛傝偄偭偦偆媮傔傜傟偰偄傞偺偑僌儘乕僶儖壔偟偨悽奅丅偩偐傜偙偦丄僼儔儞僔僗僐揑惗偒曽偺拠娫偵側傝偨偄偲偄偆庒幰偨偪偑懕乆傗偭偰偔傞乧丅偙傟偼偨偩偺柌憐偐丄栂憐偵偡偓側偄偺偩傠偆偐丅偼偭偒傝偟偰偄傞帠偼丄岞偵僼儔儞僔僗僐偺惗偒曽傪愰尵偟偰偄傞巹偨偪偺乽偁偐偟乿偺幙偑栤傢傟偰偄傞偙偲偩丅
彚柦扴摉 懞忋丂朏棽
|