フランシスコ
伊能 哲大
最近、小田垣雅也氏が『ネオロマンティシズムとキリスト教』で、あるいは門脇佳吉師が『魂よ、目覚めよ』のなかで、非常に簡単に言ってしまえば、「美的感動」と信仰の関係性を取り上げている。私もこの考えに引かれる部分がある。私自身、以前は毎冬ごとにフィレンツェのウフィッツィ美術館に一週間ほど通いつめ、中世後期からルネサンス期のいわゆる宗教絵画をそれこそむさぼるように味わったり、フランツ・リストの後期のきわめて簡潔であるが、複雑な響きを持つ宗教的ピアノ曲をきわめて抑制された心で、しかし、そこに込められた宗教性を思いながら弾いたことがある。それはまさに神秘的体験であった。
優れた芸術作品に接したときに感じる感動は、超越者に出会ったときの感動と重なり合う部分があると思える。つまり、優れた芸術作品には「美」があるから、芸術作品なのであり、人に感動を与えるのだろう。しかし、人によって「美」の定義は同じではない。私の感じる「美」が他の人の感じる「美」と同じであるということは言えないだろう。むしろ、異なるものである。「美 」とは何かを定義することは非常に難しい。しかし、「美的感動」あるいは「美的経験」はそれ自体すべての人に共通のものである。信仰もある意味でこれと同じことが言えよう。神という絶対的、無限的な超越者に対する、有限な人間の理解は厳密に言って同一にはならない。しかし、「神体験」、「信仰体験」は、その内容を問うことなく、その体験、あるいは経験というその事実そのものは同一のものである。それゆえ、かならずしも小田垣氏や門脇師と同じ意味ではないだろうが、「美的感動」とそれと深くかかわる「美的経験」には、神的なもの、神秘的なもの、ひいては信仰の問題を考える大きな契機があると私も思う。 」とは何かを定義することは非常に難しい。しかし、「美的感動」あるいは「美的経験」はそれ自体すべての人に共通のものである。信仰もある意味でこれと同じことが言えよう。神という絶対的、無限的な超越者に対する、有限な人間の理解は厳密に言って同一にはならない。しかし、「神体験」、「信仰体験」は、その内容を問うことなく、その体験、あるいは経験というその事実そのものは同一のものである。それゆえ、かならずしも小田垣氏や門脇師と同じ意味ではないだろうが、「美的感動」とそれと深くかかわる「美的経験」には、神的なもの、神秘的なもの、ひいては信仰の問題を考える大きな契機があると私も思う。
思うに、フランシスコのなかで「美的感動」あるいは「美的経験」は、非常に大きな、いやむしろ本質的なものであるかもしれない。彼の回心の過程においても、「美的感動」にかかわるものがある。彼がペルージアとの戦いで捕虜になった後、重い病を患ったが、回復すると、一つの大きな「美的経験」をしている。その間の事情は伝記のなかで次のように書かれている。
「彼の健康がわずかでも戻ってきて、仲間の助けに支えられて動くことができるようになると、周囲の田園地帯全体を見渡した。しかし、彼がそれまで望んでいた美しい風景は退屈なものとなり始め、そのような物事を愛する者をきわめて馬鹿なやつと考え始めた」(シュパイヤーのユリアヌス、『伝記』二)。
この「美的経験」はいわば否定的なものであるが、従来の彼の心のあり方が変わり始めたことを象徴するきわめて重要なものである。単なる自然美のなかに美しさを見いだせなくなったフランシスコが描かれているわけである。
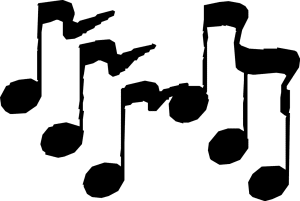 このような経験は我々にもあるだろう。非常に単純化していえば、強い光を見ると、しばらくは目がくらみ、まわりのものが見えなくなる経験をした人も多いであろう。フランシスコの「美的経験」はまさにそのような種類であろう。自然美以上に美しいものを直感的に感じてしまっている彼は、もう自然美をそのものとして味わうことができなくなってしまった。その後の彼は自然美そのものを美とは考えていない。「鳥への説教」にしろ『太陽の歌』にしろ彼は自然を愛したのではなく、自然にあらわれた神のわざを見ているのである。 このような経験は我々にもあるだろう。非常に単純化していえば、強い光を見ると、しばらくは目がくらみ、まわりのものが見えなくなる経験をした人も多いであろう。フランシスコの「美的経験」はまさにそのような種類であろう。自然美以上に美しいものを直感的に感じてしまっている彼は、もう自然美をそのものとして味わうことができなくなってしまった。その後の彼は自然美そのものを美とは考えていない。「鳥への説教」にしろ『太陽の歌』にしろ彼は自然を愛したのではなく、自然にあらわれた神のわざを見ているのである。
いずれにせよ、この神の創造のわざへの「美的感動」は、フランシスコ会の一つの霊性となっている。この霊性を、論理的に言語表現しようとしたのが、十三世紀の偉大なスコラ学者のひとりで、フランシスコ会の第七代目の総長を務めたボナヴェントゥラであった。ボナヴェントゥラはその『魂の神への道程』のなかでその思想をあらわしていると言ってよいであろう。
ボナヴェントゥラはこの書の第二章のなかで、次のように述べている。
「すべてのものは美しく、何らかの仕方で楽しみをもたらすものであり、美しさと楽しみとは釣り合いなしにはなく、また釣り合いはまず第一に数のうちにある。すべてのものが数的であることは必然である。そして、このため『数は創造主のこころのうちにあってはもっぱら範型であり』、事物のうちにあっては、もっぱら知恵に導く痕跡である」(Ⅱ・一〇)。
ここで述べているのは、原則的に自然美の問題であり、さらに、ピュタゴラス、プラトン、アウグスティヌス的な「釣り合い」の概念を使用しており、彼の独創的な考えとはいえないが、美の必要条件である釣り合いが数に基づくものであって、その数が神と深い関わりがあることを述べているのは興味深い。結局、数という純粋に抽象概念は、神秘的なもの・神的なもののある種の表現形式であるかもしれない。その意味で言えば、文学のなかで「詩」はもっとも抽象的であり、あらゆる芸術のなかで「音楽」はもっとも抽象的であるので、神的なものの表現手段としては最適なのではないだろうか。実際、古代・中世的な伝統によれば、音楽はピュタゴラス以来、数と深い結びつきがあるので、音楽の持つ抽象性は神的なものの表現形式として、優れたものであるに違いない。
このように見ていくと、フランシスコが実に音楽、特に歌を愛したのはきわめて重要な意義を持つ。例えば、『三人の伴侶の伝記』三三で次のように書かれている。
「フランシスコたちがマルケ地方を旅しているとき、彼らは主において非常に喜びました。フランシスコは大きな、はっきりとした声でフランス語で神の賛歌を歌いました。そして、全能なる方のよさを称え、祝福しました」。
「フランス語で歌った」というのは実に象徴的である。詩と旋律からなる音楽の一形式である歌が、神的なものを表現する最上の手段でありうることは先にも触れたが、フランシスコにとって、またウンブリア地方の人々にとっては、フランス語-もちろん、現在のフランス語でなく、プロヴァンス地方の言語であろうが-は外国語であり、意味が明瞭に分からなかったであろう。しかし、それはまさに、言語が意味という具体性を脱却し、リズム及び響きに還元される結果、日常性を脱却し、神秘的なものへ超越するための助けとなりうるものである。
また、『ペルージアの伝記』四三では、
「主の栄光のために、私の慰めのために、そして私の隣人の教化のために、新しい『主の賛美』の歌を主の被造物のために作りたいのです」。
ここで言っている歌は文脈上、『太陽の歌』であるが、神的なものを表現するために歌を作ることをはっきりと述べている。神への感動が歌という美的表現になり、この「太陽の歌」は聞く人々-残念ながら、フランシスコのつくったメロディーは伝えられていないが-に、美的感動を与える。まさに、神的なものへの感動と美的感動は美的表現を通して結びついてくる。美的感動が神的なものへの感動と結びつくなら、美それ自体は、類比的に言って神自身と重なり合う部分があるのではないか。しかし、神自身は無限であるから、神を規定、定義することはできない。美はむしろ、主語を規定するためのものである。そのため、神は美によって定義されることはできず、「神」と「美」は絶対的に重なり合うことのないものになる。その結果、ボナヴェントゥラは『魂の神への道程』の最後の章で、擬ディオニシオスの否定神学の影響を強く受けて、「闇」という語をキータームとして使用している。まさに、言表しえないものを論理的に言語表現しようとすれば、「闇」としか表現しようがないかもしれない。
しかし、別の観点から見ると、それとは異なったアプローチが可能である。ボナヴェントゥラの初期の作品であり、二十世紀の中世哲学史上の発見にかかわる、ブリュージュの手稿五一で 「存在の四条件は一、真、善、美である」と述べ、一は起動因、真は形相因、善は目的因を基礎に持つとし、「美はすべての原因を包含する」としている。つまり、一、真、善という超越的特質を含む美は、始源の存在者自身から輝き出る光そのものとなってくるであろう。 「存在の四条件は一、真、善、美である」と述べ、一は起動因、真は形相因、善は目的因を基礎に持つとし、「美はすべての原因を包含する」としている。つまり、一、真、善という超越的特質を含む美は、始源の存在者自身から輝き出る光そのものとなってくるであろう。
別の言い方をすれば、言葉の完全な意味で美しいと考えられる存在者にとって、可能態と同じく現実態とが完全に一致しているに違いない。それによって、それは善であろう。それはその本性がその本質に一致する。それによってそれは真であろう。それゆえ、その存在者は単独の一であるので、まさにその存在者は神自身と存在論的に考えることができよう。とすれば、一、真、善という特質を含む美は存在者自身と同一視することが可能になるかもしれない。
このように美を存在論的に、超越的特性を持つものと考えると、「神」と「美」は非常に密接な関係にあることが理解できるのではないか。その意味で、フランシスコが歌を好んでよく歌っていたということは、単なる楽しみのためだけでなく、むしろ自らの神体験の表現であったと積極的に言えよう。もちろん、信仰体験、あるいは神体験を詩や歌などの芸術として表現したものは、キリスト教の伝統のなかに深く根ざしたものであり、エフライムやプルデンティウス、あるいは十字架のヨハネなど枚挙にいとまないが、その中でもフランシスコは自然美を通して神的美を表現した独創的な芸術家としてとらえられるのではないだろうか。まさに、フランシスコは神体験を美的感動として表した人間のひとりといえよう。
神学本科一年
|