フランシスコ・マリア 古里 慶史郎
…ひとりでいるということ。ひとりなのは、よいこと…決して辛くも悲しくもないこと…。でも、誰にも認められない、誰もわたしを知っていない、誰もがわたしをいてもいなくても同じように扱うし、必要としてくれる様子も、存在を尊重してくれる気配もない。わたしはひとりぼっちで宙に浮遊している…まわりにはわたしと同じようなひとりぼっちの人はまったくいない…。そういうとき、ひとりでいることは恐怖に変わる。
天童荒太「孤独の歌声」より
しばらく前からぽつりぽつりとヤシの葉の屋根を鳴らしていた雨が、南国特有のスコールに変わろうとする折、漁のために網を仕込む老漁師の手伝いをしていた私は、彼と二人で海辺の小さな小屋に腰をおろして雨の過ぎるのを待つことにした。老人は無口で、時折見せる笑顔以外はうつむいてひたすら痩せた足を揉んでいる。目の前に広がる海は雨に霞んで、遠くにはカモメが低く飛んでいる。老人は「しばらく止みそうにないな」とつぶやき、暗い空から降り注ぐ強い雨を仰いで私は、少し鬱な気分に沈み込む。
一九九九年の夏。フィリピン、レイテ島の北、ビリランという小さな島。実習で滞在し、その期限がまもなく終わろうとしている頃。のどかな雰囲気の漁村で、日本から来た神学生の歓迎の嵐に巻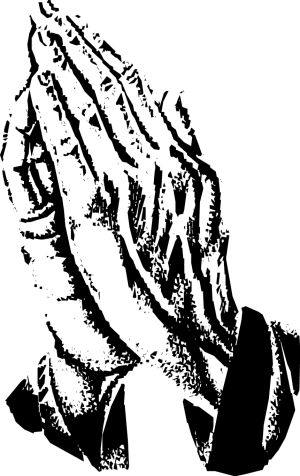 き込まれる毎日。フィリピンの人達の明るい笑顔に囲まれて、お母さんたちの楽しい井戸端会議に参加したり、押し寄せて来る子供たちと童心に帰って一日中遊び、真剣な話にみんなもらい泣きする教会の分かち合いの場に感嘆したり、青年たちと将来の夢について真剣に話し合ったり、しかしそんな時間の合間、ふと息をつく村外れの密林の中、さわさわと風の流れるヤシの木陰、星のきらめく夜の海岸に一人足を浸しながら、この足もとで死んでいった多くの人々を想う。 き込まれる毎日。フィリピンの人達の明るい笑顔に囲まれて、お母さんたちの楽しい井戸端会議に参加したり、押し寄せて来る子供たちと童心に帰って一日中遊び、真剣な話にみんなもらい泣きする教会の分かち合いの場に感嘆したり、青年たちと将来の夢について真剣に話し合ったり、しかしそんな時間の合間、ふと息をつく村外れの密林の中、さわさわと風の流れるヤシの木陰、星のきらめく夜の海岸に一人足を浸しながら、この足もとで死んでいった多くの人々を想う。
滞在中に読もうと思って持参した大岡昇平の「レイテ戦記」。感情移入の激しい私は頭を抱えていた。同著は第二次大戦の激戦地であるレイテ戦の全貌を、戦闘に巻き込まれて命を落とした全ての人々の慰霊のために、兵士の息遣いにまで肉薄する迫力で描き出した大著である。その分厚い文庫本を握り締めて、村外れを一人巡り歩いた。多くの人が死んでいったであろうヤシの林に足を踏み入れてもみた。そこは昼間でも鬱蒼(うっそう)とした繁みに視界を阻まれ、薄暗くて独りでいる不安を感じさせる場所である。前も後ろも分からなくなる世界。南国独特の巨大な濃緑の葉、蔦(つた)に足を取られ、容易に先へと進めない。時々どこからこの場所に踏み込んだかも見失いないそうになり、しんと静まった暗い密林に耳を澄ますと、ふとこの場所が戦場であったことを改めて思い出して、足元から得体の知れぬ怖さや孤独感が突き上がって来た。ジャングルの中で極限の精神状態に陥っていたであろう兵士たちの息遣いが突然耳にかかるような錯覚に陥る。嫌な先入観だなと思いつつも、奥までよく見えないほどのジャングルの繁みの影から、今にも銃弾が飛んできて私の人生を吹き飛ばすのではないかという異様な緊張感。
それからまた沢山の夢。或る日、修道院の中でフランシスコ会の兄弟たちやカテキスタと美味しい夕食と楽しい会話に爆笑し、笑い疲れて二階の自室へ上がり、静かになった部屋でその日最後の内省と黙想の時間を取り、硬いベットに横になって深い眠りに陥る頃、開け放った窓から夜中に激しい雨の音が忍び込んで来たらしい。あるいは、ひたひたと湿った霧や生ぬるい風を運んでくるような雨の気配だったのか。その雨が嫌な夢を連れて来た。夜毎に降り続く激しいジャングルの雨に濡れながら、飢餓寸前で昏倒した日本兵がうつろに目を開いたまま、やがて動かなくなる。フィリピン人の小さな男の子が、殺された母親を傍からきょとんとした目で眺めている。何も見えない暗闇のジャングルの奥から突然裂けるような叫び声が響く、そんな夢。飛び起きると、じっとりと嫌な寝汗をかいており、なんとも自分勝手で貧相な想像力に嫌気が差す。暗闇の中で半身を起こし、汗を拭きながら何がこれほどまで私の心を戦争へと掻きたてるのかしばらく考え、卓上の電気をつけてノートに書き留めてみた。…………人間の理性を吹き飛ばすほどの深い悲しみ……家族…故郷……絶望…目の前で失われていく友人たち……逃げ場のない孤独……孤独。
卓上の電気に集まる小さな羽虫を眺めながら何気なく私は孤独をいうことを考えてみた。或る人に言わせると、孤独には二重の層があるという。一つは隣人とのコミュニケーションを敢えて切って自ら創作する孤独。今の日本がそうだろうか。考えてみると、フィリピンの人に「日本の教会の問題」を問われれば、「物質主義」「個人主義」そして「孤独」とよく答えていた。この孤独は、さまざまな方法でこれを楽しむ文化が発達している現在、快適なライフスタイルの一部ともなっているようにみえる。手を伸ばせば、少なくとも近くに同じように孤独を楽しんでいる人々がいるという不思議な安心感の上に成立している快適な孤独。煩わしい人間関係を避け、独りでいることは快適である。私自身も現代日本に生きる者として身に覚えがあるのだが、それは他人との距離を広げ、往々にして福音を遠ざける。そしてその突き崩し難さに教会が四苦八苦している孤独。しかしまたもう一つの孤独。それは、存在そのものの孤独。自分が何者で、どこから来てどこへ行くのか見失う根源的な孤独。
快適な孤独がふと冷め、自分がまったく必要とされていないことに気づく。社交辞令の挨拶しか交わさない人間関係。あれほど一緒に楽しい時を過ごした友人たちが、あっけなく私の傍から立ち去り、一人ポツンと取り残される。今自分がこの場からふと居なくなったとして、誰が気に留めてくれるのか。そもそも私のことを知っている人なんて本当にいるのだろうか。あるいは、昨日まで元気だった自分に突然大きな病や事故が降りかかる。時にそれは自分が「死ぬ」ということ、自分は今ここにいるのに、まるで最初からここに居なかったかのように自分の存在が無くなるという不思議に直面させる。これらの出来事は、なぜ自分は生きているのか、なぜ生きなければならないのか、あるいはなぜ自分は死ぬのか、死なねばならないのか、自分という存在の意味を時として見失わせる。生きる意味は一つしかない。この孤独に立ち向かうことのできるものは一つしかない。それを見出す人は、今自分の身近に居てくれる人のかけがえのなさを知っているのに違いない。日常の些細な出来事、今隣にいる人への小さな思いやりのかけがえのなさを知っているに違いない。
今私はかつての絶望的な玉砕の戦場に立ち、虫の儚げな鳴き声を聴きながら、亡くなっ た多くの人々への畏敬の念を心に刻みながらも、この孤独に脅える人々の姿に執拗にこだわっている。薄暗いジャングルの中、私は、戦闘の最前線で次の瞬間体に銃弾を受けて自分の人生がプツリと切れてしまうかもしれないという恐怖、あるいは突然無意味に殺されたかも知れない人々の茫然自失、大切な友人たちとの絆が目の前で突然断ち切られた時の裂けるような叫び、自分が「生きた」ことの意味を見出せずにいたかもしれない人々の心情を考えた。 た多くの人々への畏敬の念を心に刻みながらも、この孤独に脅える人々の姿に執拗にこだわっている。薄暗いジャングルの中、私は、戦闘の最前線で次の瞬間体に銃弾を受けて自分の人生がプツリと切れてしまうかもしれないという恐怖、あるいは突然無意味に殺されたかも知れない人々の茫然自失、大切な友人たちとの絆が目の前で突然断ち切られた時の裂けるような叫び、自分が「生きた」ことの意味を見出せずにいたかもしれない人々の心情を考えた。
この恐怖と孤独を考えたとき、この地で亡くなった何十万人の人々の命が重く肩に感じられるような気がして、心情的に随分まいってしまった。キリスト者として常にイエスと共にいると確信しているはずの私でさえ、嵐で荒れた湖で(イエスが舟先にいるにもかかわらず)死の恐怖に怯えた弟子たちのように動揺する時があるというのに、戦争で亡くなった人々の心中は……しかし言葉ばかり格好の良い私自身の感傷はどうでもよい事だ。今は歴史の悲劇を避けずにそっくりそのまま心に留めるので精一杯だ。その後、私は克明かつ深刻で悲惨な玉砕描写が延々と続く「レイテ戦記」を、何度も投げ出したい誘惑に駆られながらも何とか読み上げ、ひたすら戦没者のために黙祷することを続けた。
自分でもうんざりするような長い「レイテ戦記」との付き合いが終わる頃、ビリランでの最後の数日も終わろうとしていた。先に記した老漁師とは、読書で疲れた目を休ませるために海岸へ出た折に偶然知り合った。しばらく談笑し、網の準備を手伝っているときの突然のスコールである。激しくなる雨脚にヤシの小屋の隅に逃げ込み、老人をぼんやり眺めた私は、この老人も先の戦争を知っていることに気づき、その時足を傷めていることを知った。痩せて細い足にはたくさんの傷がある。しかしながら細く折れそうなその足はよく見ると長い間潮風に曝(さら)されて傷をものともせず引き締まっていてもいる。頑丈そうだ。その足を少し辛そうに曳(ひ)きながら老人はいつも夜中に舟を出し、暗闇の中一人で漁をする。難破して帰って来ない猟師も多いと聞いた。にもかかわらず笑顔を絶やさないこの老人の人生を何だかとても愛しく想い、「お爺さん、一人で怖くない?」と何気なく聞いてみた。「さあね、怖いときもあるな。でも家に戻れば家族もいるし、それに仲間もいるんでね。海で困ったときは、みんな助けてくれるしね。」老人は訥々(とつとつ)と答え、「それにさ、神様が守ってくれるさ。ほら。」今度は胸に下げた十字架をとんと叩き、ちょっといたずらっぽく笑って、「この海はね、俺らのガリラヤ湖なんだよ。」と言った。
雨が少しあがって晴れ間も見えてきたので、老人はよっこらしょと立ちあがり、海岸へ出て行く。後を追うと、若い猟師仲間が何人か同じように海岸に出ていた。「じいさん、今日はどこへ行くんだい?一緒に魚を追い込もうか」「そうだな、今日は疲れているし、頼むとするか」。若い漁師たちは何とも言えぬ明るい笑顔で老人に応える。この若い漁師たちも、きっと自然との闘いの中で打ち負かされそうになることもあるに違いない。海の怖さや、暗闇の漁の孤独、あるいは極貧の生活の苦しさ。青白い私にわかろうはずもない。しかし仲間内で交わすこの笑顔は私の心を明るくする。
私は知らないうちに、この漁師たちと同じ生活の匂いを嗅ぎながら同じ場にたたずみ、また彼らの舟に一緒に乗り込んで微笑んでいるイエスの姿を想像してみた。
神学本科三年
|