フランチェスコ 新 直己
イタリアに『カンパニリズモ』という言葉がある。『カンパニレ』(鐘楼)から来た言葉で、愛郷心とか郷土愛とかいう意味になるそうだ。それぞれの街で聞こえてくる教会の鐘の音が微妙に違い、それを聞き慣れている者にとってはその音が一番良く聞こえる。よくお国自慢に使われる言葉だ。
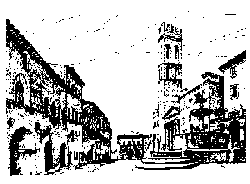
私は教会の鐘の音を聞くのが好きで、ヨーロッパの街やエルサレムに行った時などはよくお昼になると決まってあちらこちらから教会の鐘の音が一斉に聞こえてくるのが嬉しかった。現地に着いたばかりの頃の私はその音を聞く度に、今まさに自分がその国の中にいるのだということを肌をもって実感したいとよく思っていた。その国の地図、貨幣、国旗などを見ることなどでも外国にいるということが実感できるが、教会の鐘というのは耳で実感できるものでもあり、また日本ではマイノリティーの故に日頃なんとなく小さくなっているようなキリスト教徒の私も、教会の鐘の音が聞こえてくると、何だか自分がマジョリティーの一部になったようで嬉しく、その鐘の音が私を力づけてくれてさえいるようで、心強い気もした。その後引き続きしばらく一つの街に滞在していると、時間が経つにつれ、最初の頃の思いや感動も薄れていって生活に慣れっこになってしまっていることがよくあった。そんな時にまたそのお昼の鐘が聞こえてくると、ふと自分のいる場所、生活のことなどを改めて振り返ってみることがあった。きっと私にとって教会の鐘の音は何かしらの注意を促すもの(警鐘)にもなっていたのだろうと思う。
日常の生活の中でともすると慣れっこになってしまっていることや当たり前と思っていることがないだろうか。そして何かの拍子にそうでもないぞっ!!と気づかされるときがある。
瀬田に来てから早くも一月近くが過ぎてしまった。まだまだわからない事が多い中、他の神学生の兄弟たちに教わりながらも少しづつ、ミサ当番や生活の上での役割分担もするようになってきた。侍者当番などは間違えたりするものの、最近は見よう見真似でなんとかできるように(ごまかせるように!?)なってきた。それでもまだ不慣れなので戸惑うこと、思うようにいかない事が時々ある。その中の一つに、朝と昼にアンジェラスの鐘を鳴らすことがある。以前、志願期や修練期に何回かここに来たことがあるが、そのときは実際に鐘を鳴らしているということには気づかなかった。(私は鈍いので、以前はテープか何かだと思っていた。)そして、ヨーロッパやエルサレで聞いていた時はまさか(まさかカトリックに改宗して、修道院に入るなんて!)自分が鳴らすことになるとは思っていなかったその教会の鐘を、今私自身が鳴らすことになったのである。そう考えてみると不思議である...。実際自分でやってみる番になると、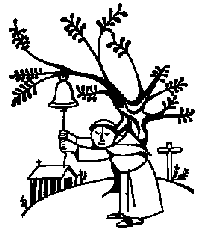 案外簡単そうに見えていても意外とこれが難しい。ロープを強く引きすぎても弱く引きすぎてもダメ、ちょっとしたこつのようなものがありそうだが、まだ修行中の身の私にはなかなかこれがうまくいかない。そのこつをつかめるようになるにはもう少し時間がかかりそうだ。そして、この鐘を鳴らしながら、まだ鐘を鳴らすこともままならないのに、自分が今瀬田の神学院にいること、キリスト教徒であること、修道生活を送っていることなどなどをも改めて不思議に思うことがある。ここに来るまでかなりの回り道をし、その間多くの人々との出会いや出来事を通し、なぜかフランシスカンと出会うことになり、志願期から始めてかれこれ早いものでこの生活ももう二年半になる。そしてなんとかここまでたどり着いた。そして、巡り巡ってまた今年もこの『小さき花』の原稿にもともとあまり無い知恵を絞って、頭を悩ませている次第である。もう締め切りなのである。 案外簡単そうに見えていても意外とこれが難しい。ロープを強く引きすぎても弱く引きすぎてもダメ、ちょっとしたこつのようなものがありそうだが、まだ修行中の身の私にはなかなかこれがうまくいかない。そのこつをつかめるようになるにはもう少し時間がかかりそうだ。そして、この鐘を鳴らしながら、まだ鐘を鳴らすこともままならないのに、自分が今瀬田の神学院にいること、キリスト教徒であること、修道生活を送っていることなどなどをも改めて不思議に思うことがある。ここに来るまでかなりの回り道をし、その間多くの人々との出会いや出来事を通し、なぜかフランシスカンと出会うことになり、志願期から始めてかれこれ早いものでこの生活ももう二年半になる。そしてなんとかここまでたどり着いた。そして、巡り巡ってまた今年もこの『小さき花』の原稿にもともとあまり無い知恵を絞って、頭を悩ませている次第である。もう締め切りなのである。
私は修練期を半年延ばしたため、これからのここでの半年は、来年の新学期までをキリスト教教養課程の講義に途中ながらも出席させてもらいながら、有期誓願者として過ごすことになる。どんな半年になるのか?それは私自身の取り組み方次第だと思う。
今までの二年半を振り返ってみると、修道生活のことを何もわからずに始めた志願期には、まずは共同体というものに直面しなければならなかった。それまでの経験から共同生活には案外慣れていると思っていた私は、志願期初期の頃に早くもその難しさを感じた。同期の志願者に、マジステルに、目上の兄弟たちに...。一人一人の兄弟が持っている歴史、文化的背景、価値観などから出てくる考え方、やり方の違いを理解できずにぶつかったり、兄弟たちをありのままでは受け入れ難く思ったことも度々あった。それまでの共同生活の経験というものは比較的気の合った者同士でとか、友達ととかで、しばらくの間一緒に住むことはあった。それでも年上の人がその中にそれほどいたわけでもなく、お互いにあまり気を使わなくても良い間柄だった。今回のように全く認識の無い、しかも目上の人たちの中でやっていくのは初めてだった。だからそのようなことも無理もないことかもしれないし、志願期に入る時は当然、共同生活にはお互いにぶつかることもあるだろうとは予想もしていた。でも実際の生活は当初予想していたものより幾分難しいものになった。兄弟たちを受け入れられず批判している時、相手を裁いている自分自身の心の中を覗いてみると、意外と自分の中にある嫌な部分を他の人たちに反映して見ているのではないかと思う。その部分をみたくないから余計に気に障る。このことから学んだことは、他人を受け入れていくことはまず自分自身を受け入れていくことからではないかということである。志願期で学んだこ とは他にもいくつか挙げられるが、まずは修道生活での共同体というか共同生活の大切さが挙げられるのでなないかと思う。このことに関してはある先輩も同じようなことを言われていた。 とは他にもいくつか挙げられるが、まずは修道生活での共同体というか共同生活の大切さが挙げられるのでなないかと思う。このことに関してはある先輩も同じようなことを言われていた。
修練期はどうだっただろうか?志願期に学んだことをまずは前提として含むのだが、この時期は祈ることの大切さをいろいろな形で学んだ時期なのだと思う。修道者にとって生活の基本となっていなければならないものは神との関係なので、その関係を作っていくには祈るということはどうしてもおろそかにしてはいけないものだろう。しかしそれまではあまり日常の中で祈るということをしてこなかった者にとって、まず、『教会の祈り』に慣れることから始まり、黙想の時間に神の前に黙して座っているということは楽なことではない。個人的に祈るときには全く何もしていないようで無為な時間に思えてしまい、ついつい何がしかの口実を見つけ、できれば無しで済ませようとしてしまう。慣れないうちは祈りの時間が過ぎるのが遅く感じられ、どう過ごしていいか戸惑いも感じていたが、少しずつ祈りの必要性、大切さ、そして沈黙の偉大さ(?)などを覚えるようになってくると、自分の方から今度は、少し神の前で時間をとろうという思いを持つ時もある。しかしそれを一年、二年やったところでそんなに簡単に祈りというものがわかるわけではない。やはりついつい後回しになってしまうものだ。まだまだ自然に祈りたいと思うようになるまでには何年もの時間がかかりそうだ。たぶんこれは一生ものなのだろう。こんな風に難しさを感じながらも、毎日の生活の中で少しずつ少しずつ神に出会っていく必要があるのだろう。そして、それと同時に自分自身と正直に向き合っていくことも学ぶ必要があることに気づかされた。つくろわず、ありのままの自分を短所も含めて受け入れていくことの大切さ、難しさも学んだ。それによって回り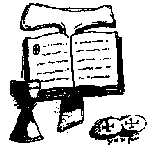 の人々も受け入れられるようになりたい。これら志願期、修練期で学んだことは今後ここの生活でどう生かしていくかそれが私にとってこれからの課題になるだろう。 の人々も受け入れられるようになりたい。これら志願期、修練期で学んだことは今後ここの生活でどう生かしていくかそれが私にとってこれからの課題になるだろう。
この二年半で、修道生活というものに幾分慣れてきた面もあるが、やはり、その逆の面のほうがまだまだある。ここの生活のリズムに早く慣れる必要はあると思うが、それと同時にいつも適度の緊張感を持っていたいと思う。ともすると流されがちになる生活の中で祈りの時間や勉強の時間でメリハリをつけ、志願期、修練期で培ってきた修道生活の基礎的な事を忘れないように、またこれも大切なことだが、生活の中で向き合っている方がどなたであるかも忘れないようにしたいものだ。時々将来のこと、勉強のこと、誓願のことなどを考えると、この先どうなるのだろう?ちゃんとやっていけるだろうか?と不安になることがある。しかし何がしかの不安を持っていることも決して悪いことではないとも思う。むしろそれらの緊張や不安が無くなっていく時こそ気を付けなければならない時ではないかと思う。そんな時この教会の鐘のことを思い出したい。自分にとってそんな時、生活の上での何らかの警鐘になってくれたらと思う。どこか自分なりのカンパニリズモを持ちたい。それはフランシスカン的な生き方に、また、キリストご自身にいつも憧れの心を持ち続け、そのことを贔屓できるようになることだ。また、ここ瀬田の鐘を鳴らしながら、フランシスカンとしての音色また、キリスト者としての音色を次第に聞き分けられるようになり、その音色が益々好きになっていきたいとも思う。もう少し欲を言えば、下手なりにも私自身がその音を響かせ、何がしかの良い影響を周囲の人々に与えられたら...。いづれはそんな人になれたらと望む。それにはまだまだ時間と修行(?)が必要になってくるだろう。まずは今できることから始めていこう。
|