管区長 ミカエル 湯澤 民夫
「昨年の研修会で、奉献生活という言葉がたくさん出てきたが、宣教会は、奉献生活ではないのではないか」
「私たちは、奉献生活という言葉に、違和感を感じる」
「確かに修道会にとっては、普通だが、宣教会にとってはそうかも知れない」
「最近、奉献生活という言葉がよく使われるようになったが、それは、イエズス会が使い始めた言葉であって、元々は、使徒的生活だったはずだ」
「それは本当ですか」
「使徒的生活だって、12世紀頃からの言葉ではないか。それ以前にも修道生活はあったから、その時はどう使っていたのか」
「ところで、宣教会、宣教会、というけど。宣教会は、本当に宣教しているのだろうか。教区長から小教区を与えられて、そこに納まっている。司牧はしていても、宣教をしていない感じがする。」
「それは、修道会も同じではないか。修道司祭も、小教区に納まって、修道会独自の在り方をしていないのではないか」
「小教区の主任司祭を通して、教区を管理しようとする教区長たちにとって、そこに納まらない修道者たちの活動や生活は、問題ではないか」
「いや、むしろ、宣教にしても、その他のことにしても、教区長が困るようであるほど、修道会や宣教会が、本来の在り方をしている証ではないかと思うが」
「そこいら辺を、来年のテーマにしてはどうだろうか」
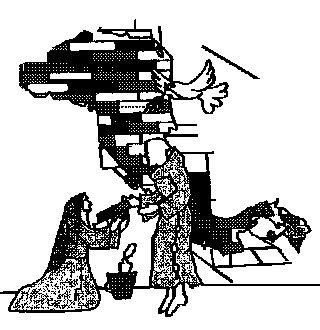
日本の修道会や宣教会の管区長や総長たちの研修会が毎年5月に開かれる。昨年の研修会は、日本における宣教会・修道会の存在意義についてのはずであった。今年は、修道会の責任者の集まり(「コングレス・2004」)がある。日本からも、男女の管区長会からそれぞれ代表を送ることになっている。研修会もそうした関係からの講演があったこともあり、ある管区長たちにとっては、どうもそのテーマからずれたものに感じられたようである。そんな中で、来年の研修会の企画を考える集まりで、上のような一連の会話になったのである。記憶が確かでないために、正しく会話を伝えているか分からないし、それぞれが正しい内容のことを言っているかどうかも分からない上に、全体の流れから、切り取った会話であるために、少々意味合いが違っているに違いない。それにしても、私たちの会は、その本来の在り方をしているのだろうか。
私たちの会は、今年(2004年9月)、管区会議があって、その準備の段階で、管区の現状を俯瞰する必要があった。「耳にタコ」的表現だが、会員の高齢化、召命の減少という現実は、はっきりしている。それは、数字だけの問題ではない。それは、気力・体力の減退、創造性の欠如と創造力の減退、安定性の追求という現象になって現れている。これを、マイナスと見るかプラスと見るか。マイナスと見ると、益々減退してゆくことになる。プラスと見るとまた別な在り方ができる。高齢化というが、高齢化した兄弟たちは、かつて第一線で活躍してきた兄弟である。更に、それ以前の記憶、かつて輝いた時の輝きを記憶という形で所有している豊かな兄弟たちである。そうしたプラスの遺産を受け継がないのは、大きな損失であろう。いずれにしても、本当の実力を把握することが大切であろう。
まだ何も始まっていないが、今から5年後の2009年は、会が創立してから800年目に当たり、その記念式典は2006年から始まる。この800年祭のキーワードの一つは、「再建」である。そして、その内容は、「本質への回帰」、本来の在り方に立ち戻ることである。それは、単なる回想ではない。聖フランシスコは、1209年に会を創設した。その4年くらい前に、1205年に、「遺言」に「こうして私は、世俗を出ました」と書かれている出来事が起こったと言われている。ということは、来年は、その800年目に当たる。これは、丁度筋肉に譬えられる。飛躍(再建)するためには、収縮(本質へ回帰)しなければならない。収縮(本質へ回帰)したら、弾け(世俗を出)なければならない。そして、飛躍(再建)する。あまり注目されていないが、ハンセン病者の顔の中に、十字架で血にまみれたキリスト顔を見たとき、彼は、家、つまり、世俗を出たのである。2005年は、本質に回帰しつつ、筋肉を収縮させる年ではなかろうか。
弾けるために。
|