Francis谷澤 律OFM
つい先頃、一人の障害を持った方と四方山話をしていたとき、その方が「海外へいっても、観光というよりも、その国が障害者にとって住みやすい国かどうかって言う事に最初に目が行きます」と言っておられました。あまりにも当然のことですが、人の持つ視点は、それぞれの人の有り方と一つになっているという事をあらためて感じました。私の視点は私がいかなる者として生きているかという事と一つになっていると言えると思います。
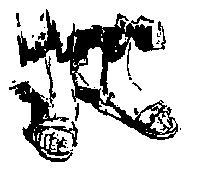
もうひとつ2000年元日に放映されたNHKの番組「子供達からのメッセージ」のなかで、一人の少女が「私の国には、『子供を産んで木を植えて家を建てる事が出来れば、その人の一生は幸せな一生だった』ということわざがあります。」と語っていました。それはきっと現代日本の中学生・高校生にとっては随分と古臭いぱっとしない言葉に響くのだろうと思い、それでこのエピソードをあるミッションスクールの練成会でも紹介した事が有ります。このことわざを紹介してくれたのはチェルノブイリのユーリアという名の少女であることがわかると、この言葉の様子が一変します。ユーリアさんは、番組放送の時点では被爆後遺症の不安の中で、民俗舞踊団の一員として一生懸命に生きていました。いつ死ぬか判らず、おそらく子供を生むというようなことは全く期待できず、生まれ育った故郷は、木を植えるどころか立ち入る事も出来ないほど荒廃した中で語られた言葉は、無理な開発競争や欲望に駆られて、もっともっと沢山の力をもとうとする世界中の大人達に対する警鐘であり、ささやかだが平和で落ち着いた当たり前の暮らしに対する願いだろうと思います。練成会に出席してくれた中学生達の多くもそれを理解してくれたようでした。一つの言葉を理解するにもどの視点に立つのかが大変重要だと思いました。
…とここまで書き溜めてあったところで、米国での同時多発テロ事件がおこりました。さまざまな意見が乱れ飛んでいます。それぞれ、おのおのの立場からはもっともな言い分だろうと思います。あるTV番組の中では一人の米国の青年が、「アメリカが武力行使してもそれは全く正当なことだ。テロは言ってみれば町の喧嘩みたいな卑怯な行為でただの暴力だが、戦争は外交手段の一つだし、きちんとルールもあるのだから暴力ではない。アメリカが武力行使をしようというのは、文句があるならリングへ上がって正々堂々と戦えといっているような事であり、まったくフェア−なことだ、」という趣旨の主張をしていました。彼の身になって事件の推移を見るならばきっとそのように見えるのだろと思います。
しかしながらいうまでもないことかもしれませんが、ある言葉が語られるとき、非常にもっともに聞こえる見解と小さき兄弟のものの見方が、いつも一致するわけではありません。それで良いのではないかという風に近頃感じます。世界中の人が小さき兄弟でなければならないわけではないのですから。ただ小さき兄弟を名乗る私達に、それに相応しい視点が欠けているならば、塩味のしない塩のようなものとなり、しょうしょう嘘臭くなります。世界中の人々がそれぞれの立場で「平和」を求めているとき、私達のピースメーカーとしての視点はどのようなものか、私達も問われているように思います。
かつて私自身が被養成者だった頃、もう少し徹底した生き方を望んで、先輩方に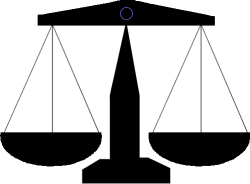 色々新しい試みの許可を願いましたが、その折り「バランスが大切である」という返事を良く頂いたものです。そうした返事を聞くたびに私の頭の中には、頼りなくゆれるヤジロベイが浮かびました。確かに人はそんなに安定したものではなく、色々なものに振り回されて揺らぎつつもどこかで危うくバランスを保っているような存在かもしれません。またそうしてかろうじて立って居られること自体が神の恵みかもしれません。ただそのときもう一つのアイディアにも付きまとわれていました。つまりそのバランスをとっているヤジロベイの支点はどこなのか、一体どこに立ってバランスを取るのかが重要なのではないか、その問いにこそラディカルな福音的勧告への聴き従いの選択があるのではないのかという思いでした。 色々新しい試みの許可を願いましたが、その折り「バランスが大切である」という返事を良く頂いたものです。そうした返事を聞くたびに私の頭の中には、頼りなくゆれるヤジロベイが浮かびました。確かに人はそんなに安定したものではなく、色々なものに振り回されて揺らぎつつもどこかで危うくバランスを保っているような存在かもしれません。またそうしてかろうじて立って居られること自体が神の恵みかもしれません。ただそのときもう一つのアイディアにも付きまとわれていました。つまりそのバランスをとっているヤジロベイの支点はどこなのか、一体どこに立ってバランスを取るのかが重要なのではないか、その問いにこそラディカルな福音的勧告への聴き従いの選択があるのではないのかという思いでした。
真にフランシスカン的なものの見方、小さき兄弟の視点というものが有るとするならば、それはそれが普遍妥当なものであるかどうかは別として、小ささと兄弟である事の両方がイエス・キリストへの信仰に基礎付けられた有り方を生きるときに自然に、私において実現する事になるのだろうと思います。視点を捜し求めなくてはいけないし、そのための生活の座の選び取りが是非必要だと思います。
|