ヨハネ・ボスコ 韓(西原) 徳 (修練者)
修練期も半年が過ぎた。志願期の特に育てていた"からし種"は、二、三メートルの高さにまで成長し、夏には綺麗な花を咲かせたらしい。本当に小さな種だったのに、これ程の大きな実りをもたら すとは思いもしなかった。信仰の薄い者だと自覚させられる。からし種は大きな実りをもたらしたが、私は実りをもたらしているのだろうか。私なりの正直な半年を振り返ってみたい。 すとは思いもしなかった。信仰の薄い者だと自覚させられる。からし種は大きな実りをもたらしたが、私は実りをもたらしているのだろうか。私なりの正直な半年を振り返ってみたい。
修練期は、どんな時?時々、自分の中に問うてみることがある。少しでも神を心で感じる時か、それとも、少しでも祈りの必要性を感じる時か、自分の無力さを感じる時か、修練期を終える時に、自分なりの答えを見つけたいと思う。今は模索している時なのかもしれない。一応、テーマとしては、神に抱かれる体験をする時としているが。まあ、綺麗な表現は置いておいて、私自身が今、どのようなことを思い、体感し、味わっているかを、「信頼をおく」、「ありのまま」、「忠実」という項目で書いてみたい。
「信頼をおく」
私は、何に対してでも信頼をおいているだろうか。時々、本当に私は信頼をおいているのか疑問になることがある。「信じています」と言いながらも、苦しい状況や、裏切られた状況になると、信頼をおくことを拒んでいる自分がいる。何だろうか。九十九%は信じ、一パーセントは疑うといったような感覚がある。主は私に信頼をおくと言った時、一%の疑いもなく、百%の信頼をおくのではないかと思う。これを信仰っていうのかもしれない。
ところで私は修練期に入って、山に登る機会が増えた。しかし、私は山が大好きな方ではない。何故なら、かつて山に登った時の経験からすれば、足が血だらけになって、歩くのさえ出来ない状態で下りてくるのが辛かったからである。では、その足の痛みを除けば好きになるのかと問われても、正直、好きとは言えない。しかし、イエスは祈るために山に登られている。偶然、祈ろうとした場所が山なのではなく、祈るために山に登られる姿がある。これを少しでも黙想し、何故祈るために山に登られたか、心で感じられたらという思いで山登りに同意した。
山で歩く速さは、本当にゆっくりとしている。生活の流れを、ゆっくりと味わいながら登っていくような気さえする。私自身は、ゆっくり歩くよりも、早く頂上に辿り着くことを未だに好んでいる。まだ山全体を味わうまでにはいかないが、そこで感じた一つの体験を書きたいと思う。それは頂上で山小屋に荷物を置き、夕食までの間、少し時間があったので、頂上近くの岩場まで上り、座って振り返っていた。
足が痛い、遅い、疲れている、イライラする、早く頂上に着きたいなど、何故痛いか、何故早く頂上に着きたいかは思い浮かばなかったが、ありのままの姿が思い出された。何か自分の姿を見る場。自分の弱さ、孤独感、無力さ、儚さなど。そんな感情を持っている私を包みこんでいる方がおられる体験をした。そこには、信頼をおいている自分がいた。イライラしながらでも、先導者に信頼をおき、神に信頼をおき、山に信頼をおいている自分。
イエスが祈るために何故山に登られたかを黙想した時、私には、弱さ、孤独、無力、儚さの中でこそ、神がイエスと共におられ、深い交わりをされているのではないかと感じられた。それにしても、不信仰な私である。
「ありのまま」
夏に黙想会に行く機会があった。富士山を目の前にした大変素晴らしい黙想の家である。そこで一人の司祭と出会った。その司祭は、私の個人指導の指導者となった。黙想が終わる前に、「何か希望はありますか?」と尋ねてきたので、私はすぐに「もしよろしければ、一緒に同じ聖書の箇所を読み、黙想し、分かち合いをしてほしい」と頼んだ。その指導者は快く引き受けてくれた。
さて、黙想も終わり、共に分かち合う時がきた。私は四十五分間、それ程何も感じていなかったのに、感じていたかのように話しはじめた。そして、私の話しが終わり、指導者の時がきた。私は、指導者が何を言われるのだろうと、胸をふくらませ、耳を傾けた。そして一言、「ねてました」と言われた。私はびっくりした。素晴らしい話をしようと、無理に感じてもいないことを口にしたのは私だけで、指導者は、ありのままを私に言った。私は指導者に、「正直ですね」と言うと、「正直じゃなかったら、分かち合いの意味もありませんよ」と切り返された。私は、ありのままじゃない。人の目を気にして、あるべき姿を無理に作っている自分がいることに気付かされる。あの指導者は、神の前でのことを、ありのままに話してくれた。神の目に生かされ、神にすべてを委ねている者の姿が見せつけられ、気付かされた。しかし大きな感動もあったことは確かである。
もう一つの気付きは、聖フランシスコの帰天祭(十月三日)のことである。晩の帰天祭が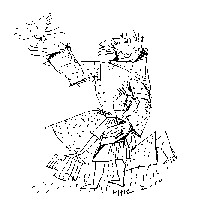 終わり、皆が解散し、静けさが聖堂に戻り、ろうそくの灯と、フランシスコの遺体(フランシスコ会の修道服)だけがあった。一人の女の子が、私に「聖堂でフランシスコさんとお話しをしに行こう!」と誘った。少しの戸惑いはあったが、同伴した。その子は祭壇の下にある、フランシスコの「遺体」の横に座り、耳元に顔を近づけ、何やら話しはじめた。「フランシスコさん、人の助けになる医者になれますように。別に医者じゃなくてもいいよ。とにかく人の助けになることなら、何でもいいよ」と。私は、その子の祈っている姿が美しくさえ思えた。本当に本心から祈ったことが私にはあったのだろうか。何か大切なものを私は見失おうとしている。この女の子は純朴さ、素朴さを持っている。その子の祈っている姿を見ている時、「天の国は、このような者たちのものである」と、心の中で聴こえてきたのを思い出す。ありのままの姿の中には、神に絶対の信頼がおかれているように感じられた。 終わり、皆が解散し、静けさが聖堂に戻り、ろうそくの灯と、フランシスコの遺体(フランシスコ会の修道服)だけがあった。一人の女の子が、私に「聖堂でフランシスコさんとお話しをしに行こう!」と誘った。少しの戸惑いはあったが、同伴した。その子は祭壇の下にある、フランシスコの「遺体」の横に座り、耳元に顔を近づけ、何やら話しはじめた。「フランシスコさん、人の助けになる医者になれますように。別に医者じゃなくてもいいよ。とにかく人の助けになることなら、何でもいいよ」と。私は、その子の祈っている姿が美しくさえ思えた。本当に本心から祈ったことが私にはあったのだろうか。何か大切なものを私は見失おうとしている。この女の子は純朴さ、素朴さを持っている。その子の祈っている姿を見ている時、「天の国は、このような者たちのものである」と、心の中で聴こえてきたのを思い出す。ありのままの姿の中には、神に絶対の信頼がおかれているように感じられた。
「忠実」
私は忠実か、不忠実かと問われれば、不忠実と答えるだろう。人の目に映るところでは、忠実に動こうとするが、見えなくなると不忠実な者になっていることがある。聖書の中で、イエスが非難しているファリサイ派の人々と同じ部分がある。
祈る時、怠けたいと思ったら怠けてしまう。怠けようとしている心を主に捧げて、「私は今、怠けようとしています。こんな私を顧みて下さい」とは言わずに、祈ることから遠ざかろうとしている自分がいる。神が私を見ていることを、喜びとしていないのだろうか。否、神が私を見ていることに、今まで気付いていなかったのである。聖堂には主はおられるが、他はおられないというように、都合のいいところで出てくる、何と自分で造り上げた神なのだろうか。人から評価されることは忠実にやろうとするが、人の目につかないところでは、いい加減にやろうとする。神の前で忠実であれば、人が見ていようが見ていまいが出来るのに、何と不自由な自分なのかと反省させられる。神が私を見ることに喜びを持てることは、最大の強さである。しかし、その喜びが持てるためには、自分が無力で弱く儚い者、取るに足りない者であることを実感し、主に信頼をおける者だけが言えることだろうと思う。
主の前でへりくだる者になれていない自分、弱いのに強がっている自分がいる。それでも、主は私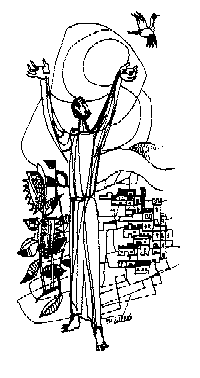 のありのままを受け入れ、抱きしめて下さっている。何とも感動してしまう。それにしても不忠実な僕である。 のありのままを受け入れ、抱きしめて下さっている。何とも感動してしまう。それにしても不忠実な僕である。
修練は、今まで書いたような自分の姿に気付き、真正面から見つめ、それを祈りに変えていく作業のように思う。それが出発点のような気がする。深い沈黙の中で神と出会い、神が私の中におられることを一度でも体験したら、「何をしたか、しないか」の神ではなく、ただあなたがおられるだけで、涙が出るぐらいに嬉しく、感動するものである。自分の傾きに気付き、そんな自分を主に捧げられたらと、日々願っているが、未だに怠け癖は治っていないのが現実である。
これは、"からし種"に勝ちを譲った方が、正解かもしれない。
|