村上 芳隆 (召命担当)
「あなたがおいでになる所なら、どこへでも従って参ります。」(ルカ九:五七〜)と、イエスに言った人がいます。イエスの弟子になりたいと考えている人の類型がここに幾つか出ていま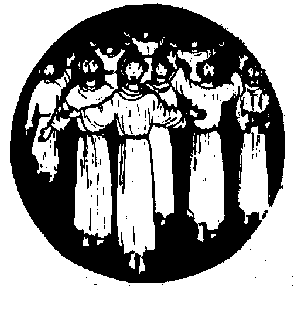 すので、少し取り上げてみましょう。第一は、ストーカー型。「何が何でも」弟子になりたいと、あらゆる困難にもめげずに駆け寄ってくるタイプ。一途さが微笑ましいくらいです。「私は、司祭(或いは修道者)になりたいです。そのためにはどんなことでも耐える覚悟が出来ています。だから、神学校(あるいは○○修道会)に受け入れてください」と自信たっぷりに言える人。「神様のために一生を捧げていきたいです」と、けなげに申し出る人。ただ、最近は不況で就職難の時代でもあり・・・。福音書のイエスは意外にも素っ気ない返事をなさっています。 すので、少し取り上げてみましょう。第一は、ストーカー型。「何が何でも」弟子になりたいと、あらゆる困難にもめげずに駆け寄ってくるタイプ。一途さが微笑ましいくらいです。「私は、司祭(或いは修道者)になりたいです。そのためにはどんなことでも耐える覚悟が出来ています。だから、神学校(あるいは○○修道会)に受け入れてください」と自信たっぷりに言える人。「神様のために一生を捧げていきたいです」と、けなげに申し出る人。ただ、最近は不況で就職難の時代でもあり・・・。福音書のイエスは意外にも素っ気ない返事をなさっています。
第二は、伝統習慣固執型。「私の父を葬らせに行かせてください。」そういうことはキチンとやらないと気が済まない人。しかし、しなければならないことを「誰かに」決めてもらわなくては安心して行動できないタイプ。言われたことはそれなりにこなすが、融通が利かない、言い換えると主体性と創造性が足りない。あるいは「大人」になっていない人。
第三は、優柔不断型。××が出来たら、◇◇があれば、○○できるだろうに!「鋤に手をかけてから後ろを顧みる者。」決断を下すことが出来ないタイプ。自立した人間として責任を担うことが出来ない。あるいは、当たり前の礼儀や伝統習慣を、やらないこと、出来ないことの言い訳に使ってしまうタイプ。
以上の類型化はあまりに単純化しすぎだと思いますが、召命担当者として3年の間に接した多くの若者たちの印象と重なる部分があります。勿論、このような第一印象から、関わりを通してもっと深いモノを持っていることを気づかせてくれる人、成長していく人たちも大勢いました。
四月の初め、カトリック新聞社から広告の件で電話が来ました。昨年の四月に広告を依頼したの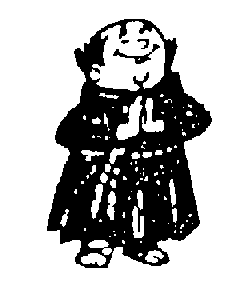 で今年はどうしますか、という問い合わせでした。今年もお願いしようと準備していたので話はすぐ決まりました。昨年度の広告は、「黙想会の案内」でした。召命チームで企画した瀬田修道院での毎月一回の一泊二日の「黙想会」宣伝でした。ただ、今年は、「静修のおさそい」としました。 で今年はどうしますか、という問い合わせでした。今年もお願いしようと準備していたので話はすぐ決まりました。昨年度の広告は、「黙想会の案内」でした。召命チームで企画した瀬田修道院での毎月一回の一泊二日の「黙想会」宣伝でした。ただ、今年は、「静修のおさそい」としました。
一九九九年秋、「召命の集い」とカトリック新聞に広告を出して黙想会を企画しました。その時、問い合わせが二〇件ほどあり、実際に参加した人は一二名ほどでした。企画としては成功しました。しかし、問い合わせの中には、「(司祭や修道生活の)召命については特に考えていないが、三〇代後半の男性が参加できる黙想会を捜している」というのがあり、考えさせられました。それで、年が明けて二〇〇〇年度から対象を二〇歳以上の男性という条件だけにして、誰でも、既婚者でも、一回だけでも参加できるように配慮しました。毎月2人から4人の参加者で、こぢんまりとした集いでした。せっかくですから、毎回、聖フランシスコを少し紹介しました。静かな雰囲気の中で過ごせるように配慮し、普段とは違った週末の時を参加者に提供することが出来たと思っています。
今年(二〇〇一年)、「黙想会の案内」から「静修のおさそい」と名称を変えた理由は、「黙想会」という言葉で「ありがたい話が聞ける(聞かされる)」という印象を与えることを避けたいからでした。とにかく静かな雰囲気の中で祈りたい、あるいは霊的指導を受けてみたい、と望む人たちに小さな場を提供することが主旨でした。つまり、私たちが意図したことは、ありがたい話や勉強になる話を聞かせることではなく、神の招きを自分の生活の中で聴きとり(読みとり)、自分らしい応え方が出来るようにサポートすることでした。神様からの呼びかけと招きに自分なりに応える道を共に識別していくお手伝い、同伴が出来ることは私たちにとっても大きな喜びであり、働きがいのある分野だと思っています。
|