神学本科三年 フランシスコ伊能哲大
フランス・ ロマン派にラマルチーヌという詩人がいる。彼は「前奏曲」、「祈り」、「夢」などの数多くの詩を残している。そして、「孤独の中の神の祝福」という詩がある。彼は宗教的な表題を付けた詩を多く書いている、彼の政治的立場は共和派であったにもかかわらず。だが、ここでは彼の詩を問題にするのではない。彼の詩から霊感を受けた多くの曲を残した、同時代の作曲家、そして後にフランシスコ会第三会士となるフランツ・リストの同名の音楽を問題にする。 ロマン派にラマルチーヌという詩人がいる。彼は「前奏曲」、「祈り」、「夢」などの数多くの詩を残している。そして、「孤独の中の神の祝福」という詩がある。彼は宗教的な表題を付けた詩を多く書いている、彼の政治的立場は共和派であったにもかかわらず。だが、ここでは彼の詩を問題にするのではない。彼の詩から霊感を受けた多くの曲を残した、同時代の作曲家、そして後にフランシスコ会第三会士となるフランツ・リストの同名の音楽を問題にする。
「孤独の中の神の祝福」というフランツ・リストのピアノ曲は「詩的で宗教的な調べ」という彼のピアノ独奏用曲集の三曲目に位置する。ちなみに、この曲集の「祈り」、「アヴェ・マリア」、「主の祈り」などは私がよく弾く曲である。特に、この曲集の最初の曲である「祈り」は、静寂な祈りではなく、魂の叫びとも言える、そしてあらゆる難関を前にしてそれを克服しようとするきわめて力強い「祈り」である。
ところで、「孤独の中の神の祝福」は大変な難曲である。嬰ヘ長調という調性もさることながら、弱音での速いパッセージ、幅広いアルペッジョ、十度以上にも及ぶ和音などピアノのテクニックはきわめて高度なものを要求している。しかも、それはある種の「エチュード」に見られるような技術のための技術ではなく、表現のための技術なのである。しかし、ここで言葉によって表現しても仕方があるまい。この曲については、CDなどで比較的手に入れやすい筈なので、実際に聞いていただくことにして、別のアプローチからこの曲について触れてみたい。
私たちは、「孤独」の中でなにを思うだろうか。さびしさか、悲しみか、あるいは平安か。「孤独」と聞いたときに、悲しみをおぼえるのは私だけだろうか。「孤独」は、まさに一人きりの状態である。「人間」は「孤独」の中では生きていけない。人の間にある存在である「人間」は関係の存在である。関係の存在があるからこそ、「私」と他者が存在する。「私」は他者との関係においてのみ「私」なのであって、その関係性をぬきにして「私」は語りえない。「私」は「私以外の何者か」との関係においてのみ「私」なのである。「私」が「私」であることは、この関係性の中でのみ成立する。まさに、エリク・ドイルが『人間とは定義するなら、「他人とともにいる存在」、あるいは「他人のための存在」である』(エリク・ドイル 「現代に生きる『太陽の賛歌』」、サン・パウロ、2000年、306ページ)というのは正しい。
音楽もまさにそうである。ある曲の中のある一つの音は、それ以外の音あるいはその曲全体との関連においてのみ意味を持つ。たとえば、「ハ」という音は「ハ・ホ・ト」の中での関係と「ハ・ヘ・イ」の中での関係とでは、明確に異なった意味を持つ。しかし、「ハ」なしには「ハ・ホ・ト」も「ハ・ヘ・イ」も成立しえない。逆に、「ハ・ホ・ト」という関係性なしには「ハ」の音は存在しえない。「ハ」が「ハ」であるためには他の音との関係性の中でのみ成立する。
また、旋律もそうである。旋律は一つ一つの音の高さのつながり、およびリズムにより構成されるが、そ れ自体で一つのまとまりを作る。そして、そのまとまりはそれを構成する音が一つでも欠けると壊れてしまう。たとえば、ベートーヴェンの第五交響曲、第一楽章の第一主題、有名な「ト・ト・ト・変ホ」の旋律は、たとえば、「ト」の音が一つでも欠けたら、あるいは「変ホ」が「ヘ」になったら、まったく異なった旋律になってしまう。つまり、旋律が成立するためには、ある一つの音はそれ自体で存在しながら、かつ他の音との有機的な関係を保たなければならない。 れ自体で一つのまとまりを作る。そして、そのまとまりはそれを構成する音が一つでも欠けると壊れてしまう。たとえば、ベートーヴェンの第五交響曲、第一楽章の第一主題、有名な「ト・ト・ト・変ホ」の旋律は、たとえば、「ト」の音が一つでも欠けたら、あるいは「変ホ」が「ヘ」になったら、まったく異なった旋律になってしまう。つまり、旋律が成立するためには、ある一つの音はそれ自体で存在しながら、かつ他の音との有機的な関係を保たなければならない。
このように、音楽は関係性の中で成立してくるものである。確かに、先年亡くなったアメリカの作曲家スティーブ・ライヒに「in C」という曲があり、これは「ハ」の音のみで構成され、他の音との関係性は存在しないが、音高や音価が異なり、やはり関係性の中で成立しているといわざるをえない。
音楽が関係性の中で成立するとすれば、関係性の喪失としての「孤独」を本来表現し得ない。関係性を基盤にしたものは関係性が本性的であるので、関係性の喪失を充全的にあらわし得ない。これは私たちの思考が結局は既存のものを基礎に成立してくることと同じである。私たちは存在しないものを存在しないものに従って想像することはできない。常に自らの経験の中から想像してくる。たとえば、宇宙人についてのイメージ、怪獣についてのイメージについて考えてみればわかるだろう。そこにあるのは単に既存のものの組み合わせにすぎない。この意味で、音楽は「孤独」を本来的に表現できない。しかし、「表現できない対象」と「表現する努力」とは本質的に異なる。なにを当たり前のことを言っているのかと思うであろう。だが、この点がきわめて重要なのだ。「表現する努力」において人間の持つ可能性がある。これは人間の精神のきわめて中心的な要素である。
「表現できないもの」をあえて表現しようとすることは、人間のきわめて自然本性的であり、かつ理性的な試みである。我々が「三位一体の秘義」を考察しようとする試みはまさに同じである。人間は表現できないものをあえて語ろうとする。確かに、ウィトゲンシュタインが「論理哲学論考」の中でいうように、「語りえないものには沈黙しなければならない」ということも言いえる。しかし、彼が「論考」の中で問題にしたのは、その「語りえないもの」なのである。「語りえないもの」、「表現できないもの」をあえて語ることに、人間の探求がある。これは徹底して観念の領域の作業である。つまり、目に見える具体的なものを扱うのではない。感覚的なものと隔絶した領域での作業である。
さて、リストの「孤独の中の神の祝福」であるが、主題は嬰ヘ長調の主和音でできている。テノール声部に単音で嬰ハ、嬰ヘ、嬰イ、嬰ハと上昇する。この主題が次に出てくるときには、一オクターブにわたるアルペッジョで表現され、三度目に出てくる前半部のクライマックスでは実に二オクターブにわたるアルペッジョで演奏されてくる。ここに重要なポイントがある。アルペッジョは「分散和音」と訳されるように、時間的差異を持って次々に奏される音群である。「和音」が複数の音を同時に奏することで成立するのと異なり、和音を構成する音を順次奏していくことになる。
「和音」が一つのまとまった響きとして耳に聞こえてくるのと異なり、人間は「分散和音」を一つ一つのばらばらの音として聞くのではなく、それぞれの音の関係性のうちに響きを感じるのである。まさに、「分散和音」は関係性のうちに成立するものである。その意味で、リストが単音であらわした主題が、次第に一オクターブ、二オクターブとアルペッジョを絡めて展開していくのは、ひとつの「孤独」な音が関係性の中でその響きを豊かにしていくことを示しているのである。一つ一つの音が実は関係性の拡大の中でその音のもつ豊かさを増していくことを表現しているのである。
関係性の中で表される音はその関係性に含まれる音すべてを内在しているのである。逆に、その関係性はその関係性の中に含まれてくる音が一つでも欠けることで崩壊してしまうのである。そして、複数の関係性はまた同じように相互に深い関係を持つ。
次に、「孤独の中の神の祝福」は三つの主題で構成されている。前述したのは第一の主題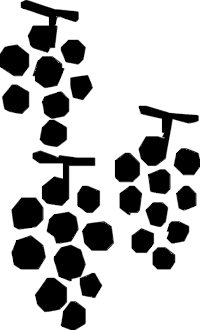 である。第二の主題はニ長調で、付点音符と跳躍する下降音形が特徴的なものである。第三の主題は変ロ長調で、四分音符を中心に二度ずつ順次に上昇する音形が特徴的なものである。このように、この曲の三つの主題は古典的な意味での関連性をまったくもたないものである。これにはどのような意味があるのだろうか。 である。第二の主題はニ長調で、付点音符と跳躍する下降音形が特徴的なものである。第三の主題は変ロ長調で、四分音符を中心に二度ずつ順次に上昇する音形が特徴的なものである。このように、この曲の三つの主題は古典的な意味での関連性をまったくもたないものである。これにはどのような意味があるのだろうか。
ところで、「孤独」の中で、心の落ち着き、いわば平安を感じることもある。孤独は関係性の喪失であるにもかかわらず、なぜ平安を感じるのか。しかし、イエスが祈ったのは「孤独」のうちでなかったか、荒野にせよ、ゲッセマネにせよ。フランシスコが祈ったのはラベルナ山中ではなかったか。アントニオが最晩年を過ごしたのは木の上ではなかったか。フランシスコの伴侶たちは小さな穴の中で祈り、生活したのではなかったか。
彼らはなぜ孤独になったのか。それは祈りのためではなかったか。彼らは祈りのためになぜ孤独になったのか。実に単純なことであるが、そこで神に出会うためであった。孤独は神に出会う場でもある。それが平安を感じる理由ではないか。つまり、「孤独」は実は孤独でないのである。「孤独」それ自体はすでに神との関係性を内在する場なのである。そして、そのような「孤独」の中では互いに対立するものが調和を保ちうるのである。マルコ福音書一章十三節に、イエスは「野獣といっしょにおられたが、天使たちが仕えていた」とある。また、砂漠の隠修士たちを描いた絵画にも野獣といっしょにいる隠修士が描かれている。「孤独」のこの新約聖書的神秘、あるいは聖人伝・絵画における神秘は、「孤独」の内容を豊かにするものである。
さて、「孤独の中の神の祝福」の三つの相互に異なった主題は、古典的な意味での関連性をもっていないにもかかわらず、ひとつの楽曲の中にきわめて自然に配置されている。これはまさに、今述べた「孤独」のもうひとつの側面のあらわれではないか。そうであれば、この相互に異なる三つの主題の調和は神秘をも含むものであるかもしれない。いや、これは言いすぎであろう。しかし、この調和はまさに「神秘」の類比的な表現ともみなしうる。
我々が「孤独」を感じるとき、それは「神秘」からの疎外、あるいは神、あるいは超越者からの疎外がそこにあるのであろう。それがひとつには「悲しみ」、「さびしさ」というイメージになるのである。しかし、そこに「関係性」を見出すことができれば、「平安」を感じることになる。そして、そのような「平安」は対立するものを一致させるものである。プラトン的にいえば、一致のあるところ、そこには善も真理もある。そして、美も。さらに、20世紀の偉大な神学者の一人でもある故フォン・バルタザールに従えば、美はまさに「神の栄光」にほかならないのである。
|